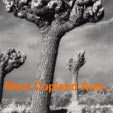 |
「Marc Copland And...」Marc Copland /hatOLOGY
米国ジャズでまとめたことがなかったので今回は、これがテーマだ。とはいえ最初に紹介するこのマーク・コプランドはスイスのhatOLOGYというレーベルから作品を出し続けているピアニストで、ちょっと聴くとユーロ・ジャズのような雰囲気を醸し出してる。2002年の録音だが、日本では今年発売された彼の最新作。リリカルなピアノは絶品だし、ドゥルー・グレスのベースはテクニックも落ち着いた質感も最高だ。マイケル・ブレッカーが2、5曲目で参加しているが、僕の好みは他の5曲に参加しているギターのジョン・アバークロンビーのほうだ。とくに「Blue in Green」は必聴の名演。 |
|
 |
「Haunted Heart & Other Ballads」Marc Copland /hatOLOGY
コプランドが、ベースのドゥルー・グレス、ドラムスのヨーヘン・ルッカートと組んだ2001年の録音だが、これは大傑作。「My Favorite Things」を3バージョン収録したり、「Greensleaves」(この曲って16世紀のリュート曲にまで遡れる)などをやっているが、その思索的なピアノ・プレイは絶品だ。コプランドはサックスからピアノに転身した人だが、最初バラードを何度も異なったコードやヴォイシングでプレイする練習したという。コール・ポーターからコルトレーンの「クレッセント」まで、さまざまな時代の曲を取り上げながらすべてに彼の「思索」を感じさせる演奏で、ちょっとこの欄で紹介するのが遅すぎた気もする。 |
|
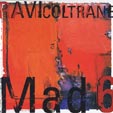 |
「Mad6」Ravi Coltrane /Eighty-Eights
僕がジャズにハマったのは17歳のとき、ジョン・コルトレーンの「Afro Blue」を聴いてからのことだ。後半のソプラノを吹き上げるフレーズには思わず涙した。マリア・カラスを初めて聴いたとき、声そのものの比類なき美しさに涙したのと同じようなものだ。コルトレーンが67年に40歳で急逝したとき、息子のラヴィはまだ2歳だったはずだ。今では父と同じようにテナーとソプラノ・サックスをプレイするようになった息子は、直接、教えることのなかった父の作品をここで2曲演奏している。ラヴィはこのアルバムで現在のジャズを演奏している。映画『モ・ベター・ブルース』を観るかのように……次の世代が、新しさをもって歴史を引き継いでいる。 |
|
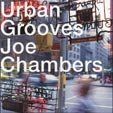 |
「Urban Grooves」Joe Chambers /Eighty-Eights
ジョー・チェンバースは60年代の「新主流派」に属するが、ドラマーなので自身のリーダー作は73年に一枚出しただけであった。もっともヴィブラフォン、マリンバ、ピアノまでやるのでただのドラマーではない。しかも編曲歴も長く、2002年に録音された本作は彼のこれまでのこうした経歴と成果の集大成といってもよいものだろう。オーヴァー・ダビングを一切していないため「シッズ・アヘッド」では、マリンバを演奏した後にそのままドラムスに移行するなんてワザも見せている。「In a Sentimental Mood」や「Stella by Starlight」等のスタンダードから自作曲まで曲想はいろいろだが、新主流派らしいアンサンブルにみちた秀作。 |
|
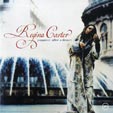 |
「paganini: after a dream」Regina Carter /verve
1995年にデビューしたレジーナ・カーターの最新の5作目。フュージョンからソウル、クラシックまで何でもやってしまうジャズ(?)・ヴァイオリニストだ。そういう器用さやウマさは、ヤバくするとユージー・メニューインだよなあ、と思っていたら本作にも1曲目でそんなメニューイン風フレーズがでてきた。でも、とりあえずこれは選曲が最高なのだ。ガブリエル・フォーレの「パヴァーヌ」や「夢のあとに」、ルイズ・ボンファの「黒いオルフェ」ほか、アストル・ピアソラ、モーリス・ラベル、ドビュッシーまで、なんかイージーなコンピものみたい。でも、曲はいいので思わず和んでしまう。僕には19世紀末の倦怠の象徴のように思えるフォーレも、ここではただただお洒落。 |
|
 |
「the legendary MARVIN PONTIAC greatest hits」Marvin Pontiac(John Lurie?) /strange & beautiful music
2001年の作品だが、最近偶然みつけた「マーヴィン・ポンティアックの伝説」。ジャケのボケた写真1枚と、いくつかの録音を残して77年に死んだ伝説のブルースマンの楽曲を発掘したアルバム……となっているが、歌もアルト・サックスもギターもブルース・ハープも全部、ジョン・ルーリーがやっている、というフェイクなアルバム。フェイク・ジャズの創始者、ラウンジ・リザーズのリーダーは、こんなことをしていたのだ。曲は、というとジャズでもブルースでもない。ポンティアックがアフリカのマリにいたとかでマリの音楽に近い曲はある。でもジャンル分けが不可能なアルバム。いまどきどこのジャンルにも属さないような音楽なんて滅多に出会えないぞ。 |
|
 |
「the grand unification thecry」Stefon Harris /BLUE NOTE
ジャケだとテクノのアルバムみたいだが、演奏しているのはブルーノート期待の若手ヴィブラフォン奏者ステフォン・ハリス。1973年生まれだから、今が旬といったところだろう。98年には、ウイントン・マルサリスの凡庸を絵に描いたようなリンカ−ン・センタ−・ジャズ・オ−ケストラの一員として来日したそうだ。ま、あそこから抜け出せてよかったろうけれどね。で、この新作はクールでかなりカッコイイ。ヴィブラフォンというとデイブ・パイクやカル・ジェイダーのラテン・ラウンジな感じなどを思い起こすが、ステフォンはもっと新しい世代を感じさせる。全曲オリジナルだが、ラテン・パーカッシヴなヴィブラフォンという感じだろうか。フロア向けにもなりそうだ。 |
|